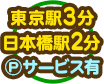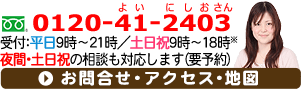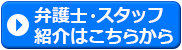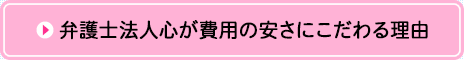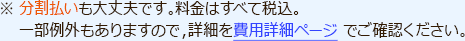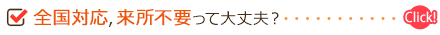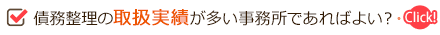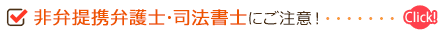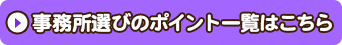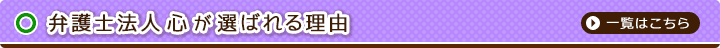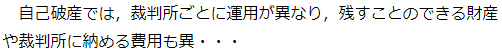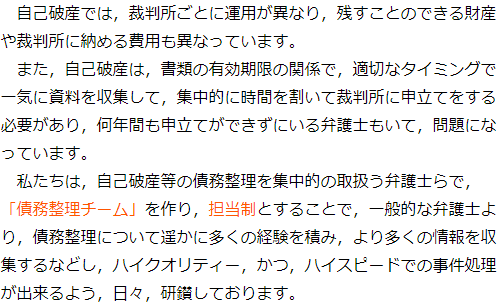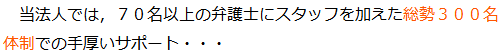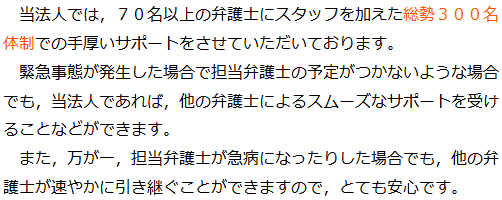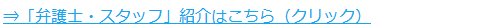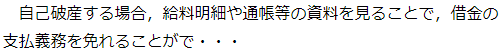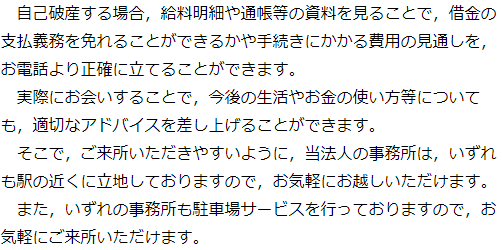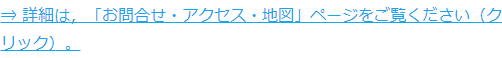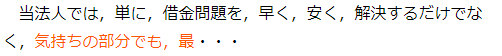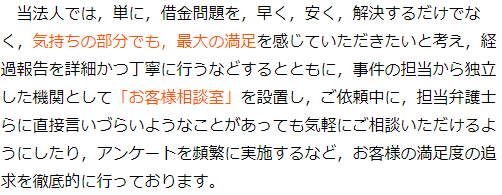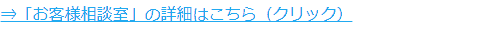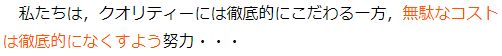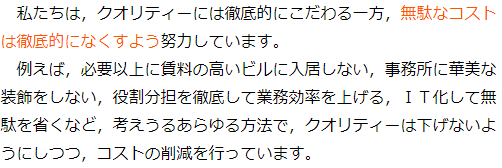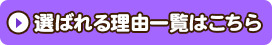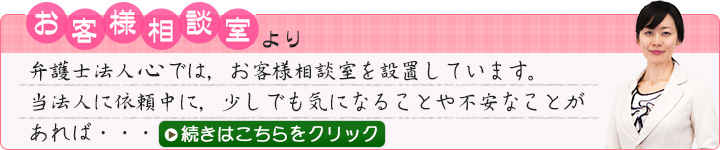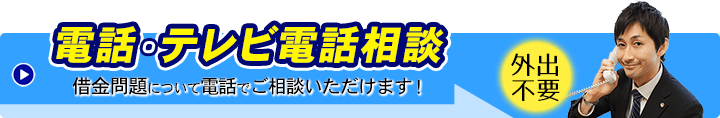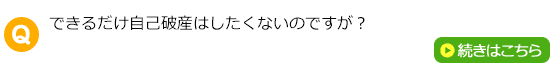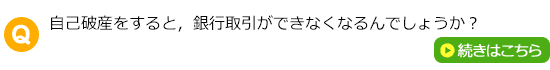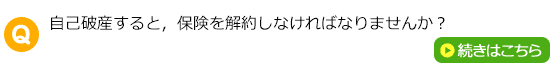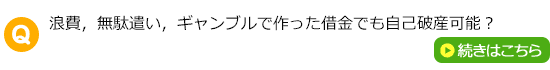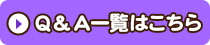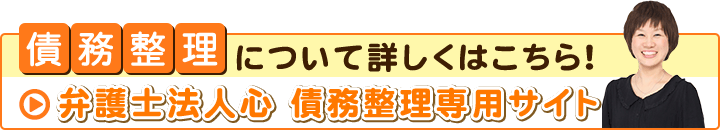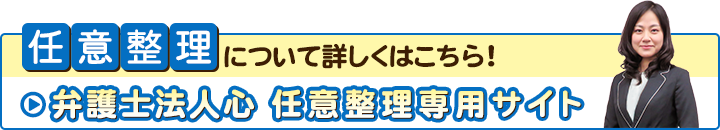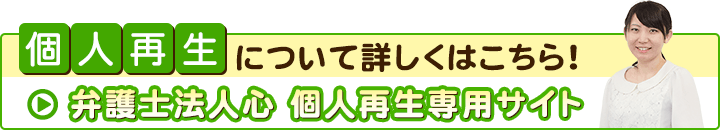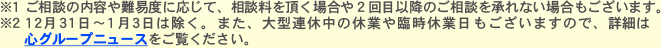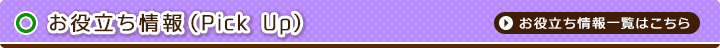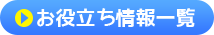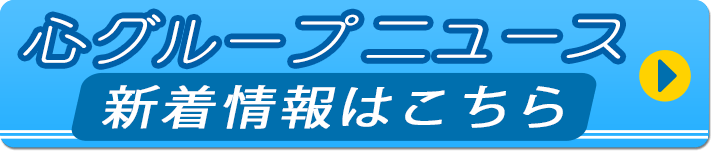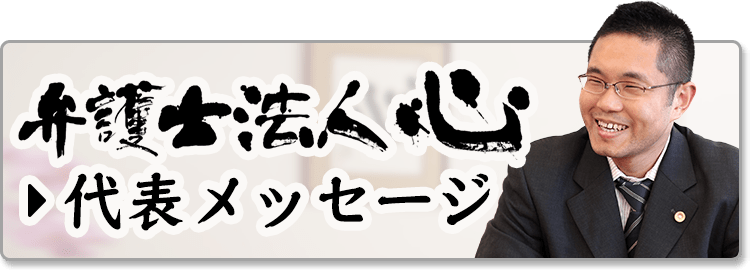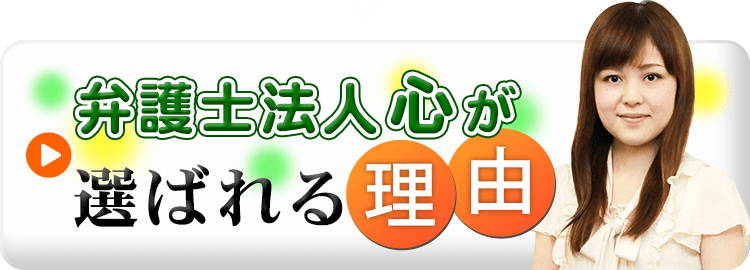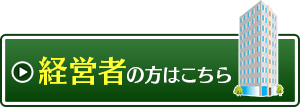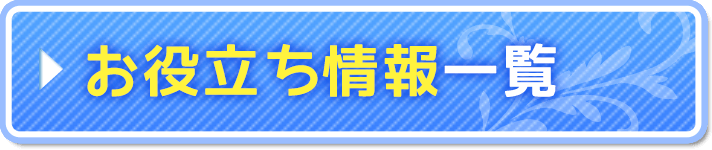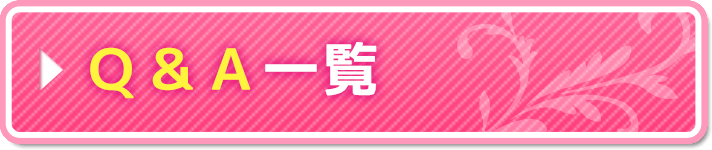サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月10日
自己破産に関してよくある誤解
「自己破産」という言葉は広く知られていますが、その内容を正確に理解している方は多くないかと思います。そして、正確に理解できていないがために、実は自己破産を・・・
続きはこちら
2025年11月27日
免責不許可事由に該当するケース
個人の方の自己破産において一番の目的となるのは、最終的に免責を許可する決定を得ることといえます。破産者は、免責決定により、破産債権について・・・
続きはこちら
2025年9月24日
自己破産しても賃貸物件を借りることは可能ですか?
自己破産をはじめとする債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載るという状態になります。信用情報機関に事・・・
続きはこちら
2025年8月13日
自己破産した場合の家族の財産
自己破産をすることで、家族に悪影響が及ぶのではないかということを懸念される方は多いと思います。しかし、自己破産をはじめとする債務整理手続の影響は、あくまで・・・
続きはこちら
2025年5月16日
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは、何といっても借金を返済しなくてよくなるというところにあります。裁判所に自己破産の申立てを行い、免責許可決定を得ることができれ・・・
続きはこちら
2025年2月10日
離婚の自己破産への影響
離婚と自己破産は全く別の手続きであるため、自己破産の手続中に離婚をすることも可能です。もっとも、離婚は単に夫婦関係を解消して別居するようになる・・・
続きはこちら
2024年11月8日
自己破産により自動車を手放すことになるのか
ローンを組んで自動車を購入する場合、ローンを完済するまでは所有権が販売会社等に留保されているケースが多いです。そのため、自己破産をする旨の連絡を・・・
続きはこちら
東京でのご相談
自己破産に関する疑問や不安などを、弁護士がしっかりと解決させていただきます。東京のアクセスが便利な場所に事務所がありますので、ご相談いただきやすいかと思います。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産申立てのために準備しなければならない費用

自己破産の申立てのためには、弁護士費用、破産申立て自体に要する費用、管財人への引継予納金、実費等の費用がかかります。
それぞれいくらくらいになるのかはケースバイケースなので一概には言えませんが、事業を行っていない個人の方が自己破産する場合は、弁護士費用が30~50万円程度、破産申立て自体にかかる費用や実費が合計5万円程度、破産管財手続となる場合にかかる管財人への引継予納金が20万円ほどになることが多いです。
2 どのようにして費用を準備するか
自己破産を検討している状況にある人が、上記金額をすぐに準備するのは難しいことが多いと思いますので、ほとんどの場合は分割払いで準備していくことになります。
自己破産することを決めた後は、各債権者への返済は止めることになりますので、これまで返済に充てていた金額分は余裕ができるはずです。
その毎月の余剰分を破産手続に充てる費用として毎月積み立てていくのが基本となります。
また、費用の準備と合わせて申立てに必要な書類も並行して準備していくことになります。
費用の準備ができるまでに必要書類の準備を完了させ、なるべく早期に申立てを行えるようにしていきます。
3 東京地裁では管財人への引継予納金を分割で支払うことができる
管財人への引継予納金20万円については、原則として申立て時に準備ができている必要がありますが、東京地裁では例外的に分割での支払いを認めています。
分割できる回数は最大4回なので、毎月5万円ずつ準備ができる状況にある方であれば、引継予納金については分割で支払うこととして、それ以外の費用の準備ができた段階で破産申立てを行うことが可能です。
なお、管財手続となるか同時廃止手続となるかについては最終的に裁判所が判断する事項です。
そのため、申立て前にどちらの手続になるのかを確定的に判断することはできないのですが、ある程度の見込みを弁護士とも確認し、費用の準備を進めていくことが大事になってきます。
自己破産ができないケース
1 免責が認められない場合

通常、自己破産の目的は、免責を認めてもらう(借金の返済義務をなくす)ことにあるかと思います。
しかし、法律上免責不許可事由が定められていることから、これに該当してしまうと免責が許可されない可能性があります。
現実的には免責不許可事由に該当していても、裁量免責によって免責されることが多いですが、免責不許可事由に該当する程度が大きい場合には裁量免責が認められない可能性もでてきますので、そのような事情が存在する場合は自己破産の手続を行うべきかよく考える必要があります。
ギャンブル、浪費、投資などを理由とする借金は代表的な免責不許可事由に該当する例ですが、短期間に収入に見合わない(返済の見通しが立たない)高額な借り入れをして、ほとんど返済できていないという場合なども免責を受けられない可能性があります。
2 非免責債権がほとんどだという場合
税金や国民健康保険料など租税等の債務、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務、養育費、婚姻費用などは自己破産をして免責が認められても、支払い義務がなくならない債務です。
これらの債務が多くを占める場合、自己破産できないわけではないものの、自己破産しても免責対象外の債務ということになるので、自己破産をする意味が希薄になります。
その意味で自己破産ができないケースだといえます。
3 自己破産が難しい場合にどうすべきか
債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生といった手続があります。
収入や支出の状況次第にはなってきますが、自己破産が難しいと考えられる場合はこれらの手続ができないかを検討すべきです。
上記2に該当する場合だと任意整理や個人再生もかなり難しいかもしれませんが、例えば租税の支払いについては分割払いを役所にお願いしてみるという方法もあります。
4 弁護士に相談
免責不許可事由に該当するおそれがある場合などは、自己破産が最適な手段なのかを自身で判断することが難しいです。
弁護士にまずは相談し、自己破産ができるのかどうか、その他の手続の方がいいのかどうかをよく検討しましょう。
自己破産の相談ではどんなことを話すか
1 自己破産の相談で弁護士が確認したいこと
自己破産の相談にあたり、どんな準備をしておけばいいのかわからない方もいるかと思います。
弁護士が自己破産の相談で確認したいことは、大きく分けると借入れの状況、収支の状況、保有している財産の状況になります。
2 借入れの状況

借入れの状況とは、どこの会社からいくら借りているのかの確認となります。
自己破産では借入先すべてを申告する必要があるので、もれなく借入先を話していただくことになります。
また、その借り入れについて保証人がついているかどうか、担保をつけているものがあるかどうかなども確認することになります。
3 収支の状況
収支の状況とは、毎月の収支がどの程度あり、生活費がどのくらいかかっているのか、返済に回せる資金は毎月どの程度あるのかの確認です。
少額の借金では破産はできませんか、という質問をいただくことがよくあるのですが、自己破産をすべきなのかその他の手続をとるべきなのかは、借金の額だけでなく収支の状況にも大きく左右されます。
収入が多くても家族が多いなどの事情により支出も多くなってしまうのであれば、返済に回せるお金は少なくなり、自己破産を選択する方向になります。
他方で、収入が多くなくても実家暮らしの場合だと余剰資金も多くなる傾向にありますので、自己破産以外の選択肢も出てくるかもしれません。
4 保有している財産の状況
自己破産をすると原則として保有している財産を手放すことになります。
もっとも、どこからが財産にあたるのか等難しい点もありますので、どの範囲で財産が残せるのかを確認する必要があります。
場合によっては財産を先に売却し、その売却金を弁護士費用や破産手続費用に充てることで早期の破産申立てを行うということもあり得ます。
5 準備しておくもの
破産の相談にあたって弁護士が確認する事項は大まかに言えば上記のとおりです。
相談日が決まったら、持ち物の案内等があるかとは思いますが、上記に関連する資料をそろえておく心づもりでおけば問題ないかと思います。
自己破産をした場合の生活への影響
1 自己破産のイメージ

多くの人が自己破産という言葉を聞いたことがあると思います。
ある程度仕方のないことではありますが、一般的に自己破産のイメージは良いものではなく、それだけは絶対に避けたいという意向をもっている方も少なくありません。
もっとも、自己破産に対するイメージや自己破産した場合の生活の変化については、実際よりも過度に重く悪いものになってると思われます。
勤務先から解雇されたり、戸籍に自己破産したことを記載がされたり…などの印象も散見されますが、そんなことはありません。
2 自己破産後の生活
自己破産すると財産を手放す必要があるというのはその通りですが、他方で、原則として99万円までの現金と生活に必要な衣服や家具は、残すことができます。
また、破産手続開始決定後に入金されるお給料や年金についても自由に使うことができます。
この2点だけを見ても、自己破産後の生活が経済的に立ち行かないものではないということがわかるかと思います。
なお、自己破産を理由として、賃貸住宅から追い出されることはありませんし、勤務先を解雇されることもありません(そもそも自己破産の事実を知られることが通常ありません。)。
もちろん、選挙権が停止したり戸籍に記載されたりすることもありません。
官報に氏名が掲載されることにはなりますが、官報の内容を逐一確認されることは通常考えにくいため、官報掲載によって日常生活に影響が出ることはほぼないといえます。
信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことにもなりますが、自己破産に限らずどの債務整理手続をとったとしても同じように登録されることになります。
3 資格制限
自己破産の手続開始決定から免責を受けるまでの期間、生命保険募集人や警備員などは資格制限を受けるため、この期間はその仕事を行うことができません。
しかし、あくまで上記期間内の話ですので、破産手続が終了した後は資格制限もなくなります。
4 生活への影響はあまりない
イメージとは裏腹に、自己破産による生活への影響は実は多くないということがわかるかと思います。
自己破産のイメージにとらわれず、そのメリットとデメリット、生活への影響を冷静に分析して、手続を選択することが大事です。
自己破産での弁護士選びのポイント
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う

弁護士の取り扱い業務は、刑事事件や、離婚事件、企業法務など多岐にわたりますが、必ずしもこれらすべてを一人の弁護士が行っているわけではありません。
弁護士にもそれぞれ得意とする分野、あまり取り扱っていない分野があります。
自己破産を相談する弁護士を選ぶ際にも、この点を意識しておくことが大切です。
2 自己破産を取り扱っている弁護士に相談する
弁護士の業務の実態については、医者の世界に例えると分かりやすいです。
例えば、風邪を引いて病院に行くというときに、整形外科に行く人はいないかと思います。
また、眼に異常を感じている人が内科に行くということもないかと思います。
これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があり、相談先はそれを踏まえて選ぶ必要があります。
例えば、刑事事件の弁護士として有名であったとしても、その人があらゆる分野に精通しているということにはならないのです。
弁護士を探すにあたって大事なのは、まずは依頼したい内容を取り扱っているのかどうかの確認です。
そして、とりわけその分野を強みとしているかどうかをチェックすることで、ある程度依頼すべき弁護士を絞り込んでいくことができます。
自己破産の依頼であれば、まずは債務整理を取り扱っているかどうかを確認してください。
債務整理の手続は、任意整理、個人再生、自己破産といくつか種類がありますので、自己破産をするのであれば、債務整理の中でも特に自己破産の経験が豊富かどうかを確認することが有益です。
3 弁護士法人心に相談
当法人では、それぞれの弁護士が担当分野をもち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。
ですので、上述した「その分野を強みとしているかどうか」という点の心配がなく、債務整理のご相談については債務整理担当の弁護士が担当させていただくことになります。
当法人では自己破産への対応にも力を入れており、当サイトのように自己破産の情報に特化したサイトもご用意していますので、安心亭ご相談いただけます。
また、債務整理のご依頼にあたっては、原則として事務所にお越しいただく必要がありますが、弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅や日本橋駅から徒歩5分圏内に立地しておりますので、東京圏に居住、ご勤務されている方には非常にアクセスがよいです。
自己破産で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人にお問い合わせください。
自己破産の手続きにかかる期間
1 申立てまでの準備

自己破産の手続きについて、法的な手続開始は裁判所に申立書類を提出することによって始まりますが、実際はその申立書類を作る期間も大事になってきます。
申立てに必要となる書類は、申立人本人の財産状況を示す資料や、収入状況を示す資料、保有している金融機関の口座の取引状況に関する資料といったものがあります。
これらの資料を、弁護士に依頼してから裁判所へ申立てるまでの間に弁護士に提出するわけですが、資料の中には一見して内容がはっきりと分からないようなものもあります。
そうした場合は、事前に弁護士から内容を確認されることもあるかと思います。
特に、銀行口座の通帳は、申立ての前2年分を提出することになるため、場合によってはかなりの取引回数となっていることもあります。
その中には、一見して内容が分からないお金の入出金も多くあるのがむしろ普通ですので、申立ての時点で内容を説明しておくことが多いと思います。
また、弁護士費用や破産手続に要する費用についても、この段階で準備していきます。
一括で費用を準備することももちろん可能ですが、個人の破産の場合は分割で準備することが多いかと思います。
こうした書類や費用の準備をどれだけスムーズに進められるかによって、自己破産にかかる期間は大きく変わります。
2 申立て後
裁判所へ自己破産を申し立てると、裁判所によって同時廃止手続か管財手続か、どちらの手続きで進められるかの振り分けがなされます。
同時廃止手続となった場合は、申立てからおおむね3か月程度で免責決定がなされ、さらにその約1か月後に免責が確定することで、手続きは終了します。
この3~4か月の間は、手続きは終わっていないものの、債務者の方がしなければならないことというのは事実上ほぼありません。
免責決定がなされる前に、免責審尋という手続きのために一度裁判所に行くことになりますが、これも基本的には本人確認をする程度のものになることがほとんどです。
次に、管財手続となった場合ですが、こちらの場合はまず破産管財人との面談を行います。
また、免責審尋はありませんが、債権者集会という手続きがあり、裁判所へ行く必要があります
債権者集会は、申立てからおおむね3~4か月後に第1回が開かれることが多いです。
1回で終わることも多いですが、複数回にわたることもあります。
債権者集会が終わると免責決定がなされ、約1か月後に免責が確定するというのは、同時廃止の場合と同様です。
したがって、債権者集会が1回で終了する場合は、同時廃止手続の場合と要する期間はあまり変わりません。
基本的には、申立てから半年以内で免責が確定すると考えてよいかと思います。
3 弁護士に確認
自己破産に要する期間の一般的なケースは上述のとおりですが、特に管財手続になる場合、事案ごとに要する期間が変わってきます。
また、費用についてどのように積み立てていくか、その場合にどれくらいかかるかは、収入等の状況を踏まえ、弁護士とよく話し合っておく必要があります。
自己破産の手続きにかかる期間について、詳しく知りたい場合は、まずは弁護士に相談して確認されることをお勧めします。
自己破産の際に必要な費用
1 弁護士費用

自己破産する際に必要な費用として、まず弁護士に依頼するための弁護士費用があります。
この弁護士費用を大まかに分類すると、弁護士報酬と実費の2つに分かれます。
弁護士報酬がどの程度になるのかは、その事案の複雑さによって変わります。
どのような場合に複雑になるかというと、その人の保有している財産が多岐にわたるため精査するのが大変な場合や、借入先が多数あるために確認に手間暇がかかる場合などがあります。
また、免責不許可事由がある場合や、破産管財手続になることが見込まれる場合には、弁護士報酬が増加する傾向にあります。
そのため、弁護士報酬がいくらになるのかを一律に述べることは難しいですが、おおむね30~50万円程度になることが多いかと思います。
次に実費ですが、これは郵便切手代や謄写料等になりますので、高くても数万円の範囲に収まることがほとんどかと思います。
2 申立て自体に要する費用
破産の申立てにあたっては、印紙と郵券の提出が必要です。
要するに自己破産を行うために裁判所側に支払わなければならない費用ということになりますが、こちらについても数万円程度と考えていただければよいかと思います。
3 破産管財人に対して引き継ぐ費用
破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。
破産管財手続になることが見込まれる場合には、この20万円についても必要になることを忘れてはいけません。
4 費用は一括で支払わなくても問題ない
これらの費用を合計するとそれなりの金額になってくるため、とても支払えないと感じる方もいるかもしれません。
しかし、弁護士費用や申立てに必要な費用については、毎月支払える範囲で積立てを行っていただき、準備ができた段階で申立てに移るということが可能です。
また、破産管財人への費用についても、東京地裁では開始決定後の分割での支払いを認めていますので、こちらについては必ずしも申立て段階で準備できていなくても問題ないということになります。
自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ
1 免責不許可事由とは

自己破産の手続きとは、申し立てる側としては、最終的に免責の許可を受けることを目的とした手続きであると言えます。
免責とは、債務の支払い義務を免除されるということで、免責許可が確定すると、それ以降は借金を返済しなくてもよくなるわけです。
しかし、法律では、免責不許可事由が定められており、これに該当してしまうと免責を受けられなくなる可能性があります。
2 免責不許可事由があると免責を受けられないのか
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に定められています。
もっとも、これに該当する行為をしてしまっていた場合に必ず免責を受けられなくなるわけではなく、裁判所の判断で第2項の裁量免責が認められて、免責決定を受けることができるケースは多いです。
そのため、免責不許可事由があるからといって、自己破産の選択肢が全くなくなるということではありません。
3 免責不許可になるのはどんな場合か
免責不許可事由に該当する中でも、特に程度が強いものになってくると、裁量免責を受けることができず、免責不許可となってしまうリスクが高まります。
自己破産の手続きを検討している方の中には、浪費やギャンブルが原因で借り入れをしている方は少なくありませんが、こうした借り入れは免責不許可事由に該当してしまいます。
ギャンブルを原因とする借り入れがごく一部で、少額に留まるような場合には、基本的に裁量免責が認められると考えられますが、かなり高額の借り入れを行い、それを一度にギャンブルに注ぎ込んで費消してしまったといった場合には、免責不許可事由に該当する中でも程度が強いので、裁量免責を受けられないリスクが高まります。
また、自身の財産を不当に減少させていたり、特定の債権者にのみ返済をしていたりといったものも、しばしば散見される免責不許可事由に該当する行為です。
こうした行為がある場合、その減少させてしまった金額、あるいは特定の債権者に対して払ってしまった金額を破産手続き内で負担することで、免責許可を受けられるといったこともあります。
4 弁護士へ相談
免責不許可事由の問題は、非常に専門的で判断の難しい部分も多いです。
そのため、ご自身で判断するのではなく、まず弁護士にご相談いただくことが大事になってきます。
自己破産の弁護士への相談で必要となる情報
1 借入先と借入額の確認

自己破産の相談にあたっては、まず借入先がどこなのかということ、そして借入額がいくらなのかということを確認しておくことが大事です。
金額については多少大まかなものになっても構いませんが、借入先については抜けがないようにきちんと整理しておく必要があります。
貸金業者からの借入れだけでなく、個人での借入れがある場合にはそれも含みますので注意が必要です。
もし保証人がついている借入れがある場合には、保証人が誰なのかについても今一度確認しておくとよいでしょう。
2 収支の状況の確認
ご自身の収入、あるいは家計全体での収入と支出の状況を確認することも大事です。
自己破産以外の選択肢がないのか、また、自己破産するにしても、現在も不要な支出を継続しているとなっては、返済のための努力を怠っているという印象をもたれかねません。
紙に収入・支出をリストアップするなどして、正確な収支状況を確認することが大事です。
3 財産状況の確認
自己破産を検討されている方の多くは、すでに預貯金が尽きている、少なくとも多くはない状態にあるかと思います。
ただ、財産は預貯金に限られず、解約返戻金のある保険に加入されている場合は、その解約返戻金も財産となりますし、退職金制度のある会社にお勤めの場合は、仮に今退職した場合に退職金がどの程度発生するのかも確認する必要があります。
このような普段あまり財産として認識していない可能性があるものも財産となりますので、注意して確認することが必要です。
4 銀行預金の確認
自己破産の申立てにあたっては、保有している銀行口座の通帳の写しを提出する必要があります。
今は使っていないというものであっても原則として提出するものがありますので、どこの口座で銀行口座を開設していたかを再確認しておくことが求められます。
また、普段記帳を行っていないために複数の取引が1つの取引として記載されている(おまとめ記帳)ことがあります。
その場合は、おまとめ部分の内訳を銀行で開示することが必要となってきます。
弁護士法人心が自己破産の対応を得意としている理由
1 自己破産は借金の問題へ対処するための強力な手段

自己破産は、手元に有する財産を基本的にすべて手放す代わりに、免責許可を受けることで、以後借金の返済を行う義務を免除してもらうという手続です。
以後の返済をすべて無くすという手続きですので、いくつかある借金の問題への対処法の中でも最も強力なものであり、最終手段とも言えるものです。
2 自己破産を依頼したいときの弁護士の選び方
一言に弁護士と言っても、それぞれが取り扱っている業務内容は、弁護士ごとにまったくと言っていいほど異なります。
犯罪に関わる弁護活動を多く取り扱っている弁護士もいれば、男女問題・家庭の問題をメインに扱っている弁護士もおり、借金の問題を中心に取り扱う弁護士もいるのです。
つまり、自己破産の依頼をする弁護士を探すのであれば、まずその弁護士が借金の問題を得意分野としているか、とりわけ自己破産の案件を多数取り扱っているかといったところに着目すべきといえます。
3 当法人が自己破産の対応を得意とする理由
当法人では、在席する弁護士が役割分担を行い、各弁護士が自分の担当分野をもっています。
ですので、自己破産に関する案件については、普段から借金の問題に集中して取り組んでいる弁護士が担当させていただくという対応をとることができます。
これにより、先ほど述べたような、その分野を得意としている弁護士が、それぞれのご相談に対応することができるのです。
もちろん、自己破産についても経験が豊富な弁護士がおりますので、安心してお任せいただけます。
4 東京都内にお住まいの方は弁護士法人心へ
当事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、地下鉄・日本橋駅から徒歩2分という便利な場所に位置しています。
そのため、ご相談の際はもちろん、ご依頼中に顔を合わせての打合せの必要が生じた際にもお越しいただきやすいかと思います。
東京都内にお住まいの方で、自己破産を検討している方は、ぜひ一度当法人へお問い合わせください。
自己破産で管財費用を捻出する必要が生じるケース
1 お金がなくても管財事件になることはある?

⑴ 管財手続になると破産管財人の費用が必要となる
お金がないから自己破産するのに、弁護士費用だけでなく破産すること自体にもお金がかかることがあるのでしょうか。
破産手続を行った場合、同時廃止手続と管財手続のいずれかに割り振りがなされますが、管財手続となった場合、破産管財人の費用として最低20万円の費用が必要となります。
⑵ 管財手続になるケース
管財手続になるケースは、まず管財人の費用を捻出できるだけの資産を有している場合があります。
東京地裁の基準だと、現金で33万円以上を有している、またはその他の資産で20万円以上の価値があるものを有している場合が、これにあたります。
では、そうした資産を有していなければ管財手続にはならないのかというと、そうではありません。
借入れの理由が、浪費やギャンブル、投資といった免責不許可事由に該当するものである場合や、破産手続を行う以前に偏頗弁済を行っていたことがある場合など、管財人による調査が必要となる場合には、その人が資産を有していなかったとしても管財手続になることがあります。
2 どうやって管財費用を捻出するのか
では、現にお金がない状態で、どうやって管財費用を捻出するのか、ということになるかと思います。
東京地裁では、最大4回の分割払いを認めています。
したがって、月々5万円ずつ破産管財人に費用を支払うことで、管財費用の捻出が可能になるということができ、毎月の収支で5万円のプラスを出すことができる見込みがあれば管財費用の支払いは可能です。
また、親族等の援助で管財費用を捻出してもらうという方法もあります。
この際、借りるという形をとることはできませんので、ご注意ください。
3 月々5万円の捻出も難しい場合
5万円ずつ分割で支払っていくことも難しい場合は、管財手続になっても大丈夫なように、申立前にある程度準備をしておくことが大事になってきます。
要は、最大4か月間で20万円を支払わなければならないということになるので、申立て時点で有している金額と、申立後4か月間の収入から捻出できる金額の合計が20万円を超えるような状態になったところで申立てを行う必要があります。
同時廃止となるか管財手続となるかは、最終的に裁判官の判断であり、絶対にこうなるという予想をすることは不可能ですが、ある程度の見込みを立てておくことが大事になります。
自己破産申立て前に手元の資産が多いと問題か
1 同時廃止手続と管財事件の振り分けに影響が出ることがある

東京地裁の基準では、現金で33万円以上保有している、あるいは預貯金が20万円以上ある等の基準を満たす場合、自動的に管財事件として取り扱われることになります。
管財事件になった場合、破産管財人へ支払うことになる費用が最低でも20万円必要となってきますので、同時廃止手続よりも経済的には不利になるといえます。
もっとも、破産制度の枠組みとしては、原則が管財事件で、例外的に同時廃止手続となる場合があるという形になっており、「管財事件は悪い手続である」という話ではありませんので、その点は誤解がないようにする必要があります。
ただ、手元の資産額が多くなり、上記基準を満たすことになると、同時廃止手続となる可能性がなくなるのは事実ですので、手元の資産が増えることでその後の手続に影響が出る可能性があるというのは確かです。
2 毎月の収入額が安定している場合はあまり問題ない
そうはいっても、毎月の収入額が安定している方の場合、費用の積み立てがありますので、このような問題が起こることはあまり考えられません。
一般的には、弁護士に破産手続を依頼すると、申立ての準備と弁護士費用の準備を並行して行うことになるかと思います。
破産の決意をした段階で、手元の現預金がほとんどないという方であれば、それ以降の給与から生活費を除いた余剰分を毎月弁護士に預け、破産手続に必要な費用の積み立てが完了したところで申立てに移るのが基本です。
このような流れであれば、余剰金はすべて破産手続に必要な費用として使われることになりますので、申立ての時に手元の現金・預金が何十万円もあるということはないはずです。
3 臨時の大きな入金が予想される場合は検討が必要
問題となり得るのは、一度に多額の入金がある場合です。
最も一般的なのものとしては、賞与が考えられます。
破産の依頼をした後すぐに賞与が予定されているような場合は、賞与の多くを破産手続に必要な費用に充て、速やかに申立てを行えば、手元の現預金を一定以下に抑えることも可能と考えられます。
他方で、それが難しい場合は最初から管財事件として申立てを進めるのか等、事前に弁護士と打ち合わせを行う必要があるといえます。
なお、手元の資産を減らすために浪費をする等の行為は当然大きな問題になりますので、絶対に避けなければなりません。
自己破産をどうしても避けたいという方
1 自己破産に対するネガティブイメージ
債務整理をしなければならない状況であることは認識しているけれども、どうしても自己破産だけは避けたいという方がいらっしゃいます。
テレビや各種報道の影響もあるのか、自己破産という言葉がもっているネガティブなイメージには相当なものがあるようです。
2 自己破産特有のデメリットはあまりない

最近ではインターネットで少し調べることで同様の趣旨が記載されたページが多数見つかると思いますが、自己破産に特有のデメリットというものはあまりありません。
自己破産のデメリットとしてよく挙げられる「ブラックリストに載る」「クレジットカードが作れなくなる」などは、借金の滞納情報を管理している信用情報機関に登録されることによるものです。
もっとも、信用情報機関への登録は、借金を滞納している時点で既に済んでいることも多いという意味では、自己破産をしたことによるデメリットというわけではありません。
自己破産特有のものといえば、「警備員や生命保険募集人など一部の職業はやめなければいけなくなる」というものがありますが、これも影響がある人は少ないと思います。
また、資格制限もずっと続くわけではなく、基本的には数か月程度ですので、資格制限が影響する職業に従事している方であっても、一時的な異動により対応できることもあるかと思います。
「家族や職場にバレる」ということを心配される方もいますが、これは家計簿の作成や退職金に関わる資料の提出が必要なためで、家族や職場に弁護士や裁判所が連絡をするというわけではありません。
そのため、工夫次第では、家族や職場に知られずに済むこともありえます。
このように、一つずつ見ていくと、意外と自己破産特有のデメリットは少なく、借金が無くなるという他の手続きにはない大きなメリットが見えてきます。
3 弁護士は自己破産を勧めることが多い
上の方で説明したように、自己破産特有のデメリットは少なく、借金が無くなり、任意整理や個人再生などと違って将来の借金の分割払いも残らないという大きなメリットがあるため、弁護士としては自己破産を進めることが多いです。
「弁護士は破産を避けたいという相談者の気持ちが分からないので、簡単に破産するように勧める」というわけではなく、しっかりとその人の人生を考えた結果として自己破産を進めているのです。
弁護士は一般の方と違って自己破産という言葉を良くも悪くもフラットに捉えているので、合理的に考えると自己破産が生活再建に一番資するだろうという考えが根底にあります。
4 それでも自己破産は避けたいという方へ
ここまでの話は十分に理解したけれども、自身の価値観からどうしても自己破産は避けたいという場合には、その旨を弁護士に伝えてください。
自己破産が可能でも、「任意整理でしっかり返していく」という方はいらっしゃいます。
弁護士の目線で、自己破産しか選択肢がないというケースは確かにありますが、他の選択肢が取れる場合は、もちろん弁護士としても依頼者の方の希望する方針で進めます。
任意整理が難しい場合で自己破産を避けたいとなると、現実的には個人再生ということになるかと思いますが、この手続も誰もが行えるというわけではなく、様々な要件をクリアできるかどうかという問題になってきますので、慎重に判断していくこととなります。
破産者が死亡した場合
1 問題となる点
破産者が死亡した場合、破産手続きの進み具合によって、その後の手続きが変わってきます。
以下で、手続きの進み具合に応じて、破産者の周囲の人(基本的には相続人になると思います。)に影響が生ずる事項に焦点を当てながら説明していきます。
2 自己破産手続の申立て前の死亡

自己破産の申立書を裁判所に提出する前に死亡した場合は、破産をしなければいけない人であったとしても破産手続き自体は始まっていないため、いわゆる破産者とは法的には全く異なります。
このような場合は、相続人としては相続放棄をすれば借金の支払義務はなくなります。
財産を売却して借金の返済をするという、本来は破産手続きが行う役割は、相続財産清算人申立てという別の手続きを相続人全員が相続放棄をした後に行います。
また、相続放棄をしなかった場合は、債務額によっては、相続人が自己破産の申立てをする必要が出てきます。
3 自己破産手続開始前の死亡
自己破産の手続きは、申立書を裁判所に提出した後、開始決定というものが裁判所から出ると、裁判所の審査が本格的に始まります。
自己破産手続開始の申立て後、破産手続開始前に債務者が死亡した場合、相続債権者、受遺者、相続人、又は相続財産の清算人等は、破産手続の続行の申立てをすることができます。
続行の申立てをすれば、一から自己破産の手続きを行う必要はなくなります。
続行のためには相続開始後1か月以内に続行の申立てをする必要があり、申立てがなかった場合は、期間経過時に当然に終了します。
4 自己破産手続開始後の死亡
自己破産手続開始後に破産者が死亡した場合は、2の場合と異なり、破産手続は当然続行することになります。
したがって、続行の申立て等を行うことなく、当然に破産手続は続きます。
これは、破産手続開始決定により、破産者は破産財団に属する財産の管理処分件をすでに喪失しており、破産者は執行債務者と同様に執行を甘受する消極的な地位しか有しないことから、利害関係人の続行の申立てを要さずに手続を続行させるべきだという考えに基づいています。
5 相続人はどう対応すべきなのか
破産手続が続行された場合、免責手続きは当然に終了します。
つまり、破産手続が続行し、終了したとしても、破産者の残した債務を相続しない、あるいは免責されて借金が無くなるということにはなりません。
また、税金、交通事故の賠償金、養育費など、自己破産をしても消滅しない借金もあります。
そのため、破産者の相続人は相続放棄や限定承認をしなければ、相続債権者が相続人の固有財産に対して権利を行使してくることを阻止できないのです。
(相続人の自宅や独自に貯めた預金などが借金の返済に充てられてしまうことになります。)
一般的に「破産する」ということの意味が「借金を帳消しになる」という意味で捉えられている傾向があるので、この点はわかりづらいかもしれません。
要は、亡くなった方が死亡前に破産の申立てを行っていたからといって、その手続が完了する前に死亡していた場合は、債務が相続人に相続されることになるので、期間内に相続放棄等の手続をとらねばならず、注意が必要ということになります。
その場合の対応につきましては、弁護士にご相談ください。
自己破産申立ての直前に現金化したものをどうすべきか
1 99万円までの現金は本来的自由財産

自由財産とは、破産手続をとった後も処分されることなく、破産者が生活確保のために利用することが許された財産のことを言います。
破産法上、99万円までの現金については、本来的自由財産とされているため、自由財産の拡張を行わなくとも、自由財産として扱われます。
2 直前に現金化した場合
破産手続開始時点で、もし、保険の解約返戻金や株式等の有価証券など、現金ではない形で資産を有していた場合、原則としてその資産は破産手続の中で処分されてしまうことになります。
そうなると、申立ての前に現金にしておけば、資産を残すことができるのかという疑問が浮かぶかと思います。
この点は難しい部分ですが、現代社会において、現金で99万円を所持している家庭はあまりなく、破産手続開始決定後の生活のために破産法が99万円の現金を自由財産として持つことを認めているのだから、直前に現金化されていたとしても、破産手続開始決定時に現金となっているのであれば、それは現金として取り扱い、99万円までの範囲は本来的自由財産とすべきであるという考え方も十分成り立ちます。
ただ、多くの裁判所では、現金化する前の状態であれば破産財団となっていたにもかかわらず、現金化することで自由財産となってしまっては債権者に不利益だということで、直前に現金化した現金については、現金化する前の財産として取り扱うべきだとしています。
3 どうすべきかの判断は弁護士に相談
資産を現金化した場合の問題は難しい部分も多いので、弁護士に相談することが必須です。
直前に現金化した場合であっても自由財産として認められるケースは現にありますし、いずれにしても現金化した部分から弁護士費用や破産管財費用といった破産手続に要する費用を捻出した場合に、それ自体を問題視されるということは基本的にありません。
そうした部分も含めて、資産をどのような状態にしたうえで申立てに移るべきか、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産で保険が解約になるのではないかとご心配な方へ
1 保険も資産

自己破産をすると基本的に資産を手放さなければならないということは、一般的にも想像しやすいところかと思います。
ただ、「預貯金が0円で、家や車をもっていない=資産が全くない」とはなりません。
なぜかというと、普段は資産だと思っていないものでも、法律的には資産として扱われるためです。
その代表的なものが保険や退職金です。
どちらも預金のようにすぐに引き出したりするものではないため、実感はわかないですが、今すぐ保険を解約したり、会社を退職したりすれば手元にお金が入ってくるものである以上は資産であるということになります。
2 掛け捨て保険は資産にあたらない
お金に換えることができるものが資産にあたるということは、解約返戻金の無い保険、いわゆる保険料が掛け捨ての保険は、解約してもお金が戻ってこない(お金に換えられない)ため、資産ではないということになります。
3 解約返戻金が少しでも発生したら資産として没収されてしまうのか
自己破産をしても、あらゆる資産が没収されてしまうわけではなく、自由財産として一部は手元に残すことができます。
何を自由財産として残せるかは、裁判所ごとに運用基準があります。
東京地裁の運用では、20万円未満の生命保険については、原則として、自由財産として手元に残すことが認められています。
したがって、解約返戻金がある場合であっても、それが20万円未満である場合は、自己破産の手続をとっても基本的に残すことができます。
なお、この「20万円未満」という基準は、保険が複数ある場合は、全ての保険の解約返戻金を合計した金額で判断します。
複数の保険に加入されている方もいらっしゃるかと思いますが、一つ一つの保険契約の解約返戻金は20万円未満であっても、合計すると20万円以上となってしまう場合は、いくつかは解約する可能性が出てきます。
4 必要があれば、解約返戻金が20万円以上でも残せる可能性がある
解約返戻金の金額が20万円を超えたとしても、必ず解約しなければいけないわけではありません。
20万円以上の財産であっても、裁判所、破産管財人が今後の生活に必要であると判断すれば、自由財産として手元に残すことができます。
例) がん保険に加入しており、今解約すると解約返戻金が30万円になる。
破産者は、過去にがんになったことがあるため、新たにがん保険に加入することができない。
→ このケースの場合、解約返戻金の金額が20万円以上であるため、原則は、がん保険を解約する必要があります。
しかし、一度がん保険を解約してしまうと、告知事項の関係で再度がん保険に加入することはできません。
そして、がん保険を解約した後に、破産者が再びがんになってしまうと、莫大な治療費を用意しなければいけず再び借金をすることになり、破産をした意味がなくなってしまいます。
こういった場合は、がん保険を継続する必要性があるということで、がん保険を解約せず手元に残せる可能性があります。
5 財団組み入れをすることで、解約返戻金が20万円以上の保険も残せる場合がある
解約返戻金の金額が20万円以上で、保険を継続する必要性が特段認められず、解約するのが適切・相当だと裁判所に判断されても、保険を残せる場合があります。
解約相当の保険でも、20万円を超える部分(30万円の保険であれば、20万円を超える10万円)を、納めることで解約を免れる可能性があります。
(納めたお金は、破産財団として扱われ、借金の返済に充てられます。これを財団組み入れと言います。)
もっとも、必ずこのような対応がなされるというわけではないので、どうしても保険を残さなければならないような事情がある場合には、弁護士に相談して別の手続を検討してみるとよいでしょう。
自己破産をすると退職金はどうなるのか
1 自己破産と退職金の問題

自己破産をすると、手元の資産は原則として残すことができず、債権者への配当に充てられることになります。
退職金制度のある会社にご勤務されている場合、退職金もその人の資産とみなされることになります。
「自己破産をすると、退職金がなくなるのではないか」
「裁判所から会社に連絡が行き、会社に自己破産することがバレてしまうのではないか」
「退職金分のお金を準備しなければ破産できないということは、事実上会社を辞めなければ破産できないのか」
という疑問に突き当たると思いますが、そういうわけではありません。
退職金がある場合の自己破産について解説いたします。
2 退職がまだ先のケース
退職金がどうなるかは、現時点で退職しているのか、退職が間近なのか、などの事情によって変わってきます。
まず、未払の退職金は、今この瞬間に退職したと仮定した場合の退職金額を圧縮して評価されます。
まず、退職がまだ先である場合ですが、この場合は、今すぐ退職した場合の退職金を計算し、その8分の1に相当する額を財産として評価する(破産時に持っていると評価する)ことになります。
破産しても原則として99万円までは失わない財産となるので、その他の財産と合わせて99万円を超えなければ、結果的に退職金は失わないことになります。
極端な例にはなりますが、理屈上は、99万円の8倍、つまり792万円までの退職金はそのまま残せる可能性がありえます。
一方で、8分の1に圧縮しても99万円を超えている場合、何も対策をしないと、退職していないにもかかわらず会社宛に請求がくることになりますが、そうなると会社に自己破産のことが露見するおそれがあります。
自己破産を理由に解雇することはできませんが、事実上会社にいづらくなるおそれがあります。
このような場合は、破産者が退職金の8分の1の金額を積立てによって支払い、会社に請求をされることがないように対策をすることがおおいです。
3 退職が間近であるケース
退職金は生活の糧となるものであり、法律上4分の3は守られています。
そのため、退職金の4分の1は失うこととなり、これは債権者への配当に充てられます。
4 すでに退職金が支払われているケース
退職金がすでに支払われていて、現金や預貯金に変わっている場合は、それは「退職金」としての扱いを受けるものではなく、現金や預貯金として扱われることとなります。
そのため、8分の1や4分の1といった圧縮をすることはできず、そのときの預貯金や現金の金額のまま評価されることとなります。
5 まずは弁護士にご相談ください
このように、退職金がある場合の破産といっても、退職金の支払い時期や、退職金の金額によって、手続の流れが大きく変わることになります。
また、持って行かれてしまうからと言って、支払われた退職金を浪費してしまうと、そもそも破産による免責ができなくなってしまう可能性があります。
金額次第では、破産以外の手続をとった方が有利ということもありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産のメリット
1 借金返済の義務がなくなる

自己破産をすることの最大のメリットは、借金の返済義務から解放されることです。
債務整理を進めるにあたっての選択肢は、大きく任意整理、個人再生、自己破産の3つに分かれます。
任意整理と個人再生では、手続き終了後もいくらかの返済義務が残ります。
しかし、自己破産で免責が認められた場合、借金返済義務が無くなりますので、返済を気にすることなく、生活を立て直すことができます。
2 借金問題を一度に解決できる
任意整理は、交渉する債権者を選ぶことができます。
そのため、一部の債権者をあえて任意整理の対象から除外して交渉することもあります。
しかし、後になって除外した債権者との関係でも返済が苦しくなり、結局改めて任意整理することになってしまったというケースも少なからずあります。
破産手続は、裁判所を介して、すべての債権者を手続きに参加させることになります。
よって、破産手続が終われば、借金問題を一括で解決することができます。
ただし、税金など、返済義務を逃れることができない債務もありますのでご注意ください。
3 財産を一部残しておくこともできる
⑴ すべての財産が無くなるわけではない
破産手続をすると、身ぐるみを全部はがされるようなイメージをお持ちの方も少なくありません。
しかし破産手続では、99万円以内の財産を残すことができる場合もあります。
また場合によっては、それ以上の財産を残すことが認められることもあります。
⑵ 車を残すことができる場合もある
例えば「仕事の都合で車が必要なのですが、破産したら車を手放さなければならないのですか?」という相談に来られる方もいらっしゃいます。
もちろん、高級外車を手元に残して破産をするというわけにはいきません。
しかし、古い型式の中古車に何年も乗っているというような場合、車の時価額は数十万円程度にまで下がっていることもありえます。
その場合、99万円以内に収まれば車を手放さずに破産できることもあります。
4 自己破産に関するご相談
以上のように、自己破産をすることにはメリットがあります。
「自己破産」という言葉にはどうしてもマイナスイメージが先行してしまいますが、自己破産は人生の終わりではなく、生活を再建するための制度です。
借金の問題に悩まれている方は、マイナスイメージにとらわれることなく、自己破産という選択も検討してみてください。
他の方法を考えた方が良い場合もありますので、状況に応じて比較検討することが重要です。
当法人では、自己破産するか否かお悩みの方には、弁護士から自己破産のメリットやデメリット、依頼者様ごとの状況を踏まえてご案内をさせていただきます。
自己破産についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
自己破産を弁護士に依頼するタイミング
1 どのタイミングで弁護士に依頼するか

自己破産は、裁判所で行われる手続きで、免責決定により、税金などの非免責債権を除くすべての債務の支払義務が免除されます。
ただし、破産手続開始決定後に発生したものについては、免責の対象に含まれません。
ここでは、主に個人の方の自己破産を念頭に置いて、自己破産を弁護士に依頼するタイミングについてご説明します。
2 延滞発生時期による区別
⑴ まだ延滞していない場合
A社からの借り入れでB社への返済を行うなど、自転車操業の状態になっていて、もう限界だと認識して弁護士に相談し、自己破産しか方法はないという結論になった場合は、直ちに弁護士に依頼することをおすすめいたします。
返済が限界となり、延滞が生じてしまった直後は、貸金業者から電話による激しい催促を受けることが多く、また、中には訴訟を起こしてくる業者もあります。
訴訟手続きに移行して判決を取られ、給料を差し押さえられると、自己破産を依頼しようにも費用を準備する目途が立たず、弁護士が受任できない場合もあります。
弁護士に直ちに依頼すれば、貸金業者に対する弁護士からの受任通知により、基本的に債務者の方への催促は止まりますし、破産手続きを行う予定であることを弁護士から貸金業者に伝えれば、通常しばらくは訴訟を起こされなくなります。
⑵ 延滞が生じてしばらく経っている場合
延滞が生じてしばらく経っている場合は、貸金業者からの催促は郵便による通知だけになっている場合も多く、直ちに弁護士に自己破産を依頼して催促を止める必要性が低くなっていることもあります。
ただし、訴訟を起こされ給料等の財産を差し押さえられる可能性はありますし、債務の調査により過払い金が見つかることもあります。
過払い金の請求には時効により消滅する制度がありますので、延滞が生じてしばらく経っている場合にも、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めいたします。
3 関係者の有無による区別
⑴ 親族等が債務の保証をしている場合
例えば夫が借り入れた住宅ローンについて、同居の妻が保証している場合は、夫と妻が一緒に自己破産を弁護士に依頼すれば問題ありません。
しかし奨学金等については、借り入れた本人の両親や親戚が連帯保証をしている場合があります。
そのようなケースでは、自己破産をすることにより連来保証人に請求が行くため、連帯保証人になっている両親や親戚に自己破産について説明を行ってから弁護士に依頼した方がよいと考えられます。
なお、親族に迷惑をかけたくないからと、連帯保証人になっている債務についてのみ返済を継続すると、偏頗弁済となり免責不許可事由に該当します。
⑵ 親族や友人からの借り入れがある場合
親族や友人からの借り入れがある場合も、事前に自己破産について説明を行ってから弁護士に依頼した方がよいと言えます。
親族や友人からの借り入れのみ返済する行為も、⑴と同じく免責不許可事由である偏頗弁済にあたります。
否認権を行使され、返済した分が取り戻される可能性もあり、支払ったことでかえって迷惑をかけてしまう可能性があります。
また、弁護士の受任後にこのような弁済が行われた場合は、依頼した弁護士との信頼関係が失われ、場合によっては委任契約の解約につながります。
⑶ 同居の家族に借金の話をしていない場合
夫婦の一方に借金があり、そのことを配偶者に話していないというケースは少なからず存在します。
この場合、上記⑴および⑵と異なり、他方の配偶者は法律上の関係者ではありませんが、債務整理の手続きについては協力する立場にあります。
任意整理を行う場合は、貸金業者と返済方法についての交渉を行うのみですので、配偶者の協力は必須ではなく、借金や任意整理を秘密にしたまま手続きを行うことも可能です。
しかし、自己破産の場合は、申立を行うための書類集めや、家計表の作成などに配偶者の協力が必要な場合がありますので、自己破産について配偶者に説明してから弁護士に依頼することをおすすめします。
仮に、配偶者には秘密にして自己破産を行う場合でも、相談の際には、配偶者の協力がなくても書類の準備等が可能かどうかをしっかり確認してから依頼した方がいいと思います。
当事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分の便利な場所にあり、自己破産の相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
JR東京駅から弁護士法人心 東京法律事務所へのアクセスについて
1 八重洲北口改札を出てください
JR東京駅から当法人の事務所へお越しいただく際には、八重洲北口改札をご利用ください。

2 八重洲北口から駅の外に出てください
改札を出たらまっすぐ進み、八重洲北口から東京駅の外へ出てください。


3 外堀通りの横断歩道を渡ってください
八重洲北口を出て左手にある外堀通りの横断歩道を渡ってください。


4 さくら通りをまっすぐ進んでください
横断歩道を渡った先の左手にある、さくら通りをまっすぐ進んでください。

5 一つ目の交差点を左に曲がってください
さくら通りをまっすぐ進み、一つ目の交差点を左に曲がってください。
「おかしのまちおか」が目印です。

6 左手のビルに事務所があります
交差点を左折してまっすぐ進むと、当法人が入居する八重洲加藤ビルデイングがあります。
1階にあるファミリーマートが目印です。
ビルに着いたら、向かって右手にあるエレベーターで6階の受付までお越しください。


日本橋駅から弁護士法人心 東京法律事務所へのアクセスについて
1 日本橋駅B0出口から地上に出てください
事務所への最寄りの出口はB0出口です。

2 歩道を右に進んでください
B0出口を出たら、右を向き、歩道をまっすぐ進んでください。

一つ目の交差点を右折してください。
郵便局を右手にまっすぐ進み、一つ目の交差点を右折してください。

4 一つ目の十字路を左に曲がってください
交差点を右折したらそのまままっすぐ進み、一つ目の十字路を左折してください。

5 前方のビル内に事務所があります
十字路を左折すると、八重洲加藤ビルデイングが見えます。
1階の道路に面した場所にあるファミリーマートが目印です。
エレベーターで6階の受付までお越しください。