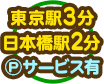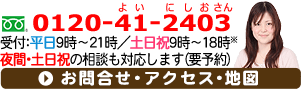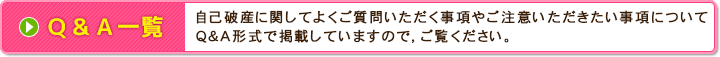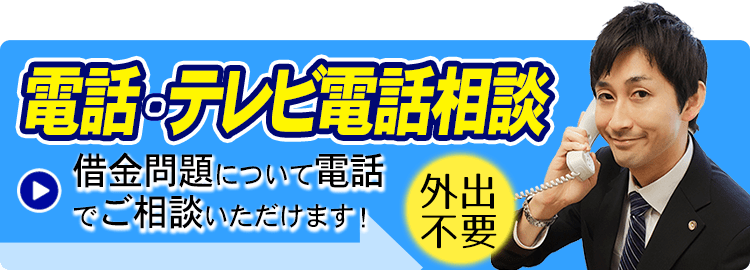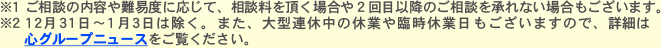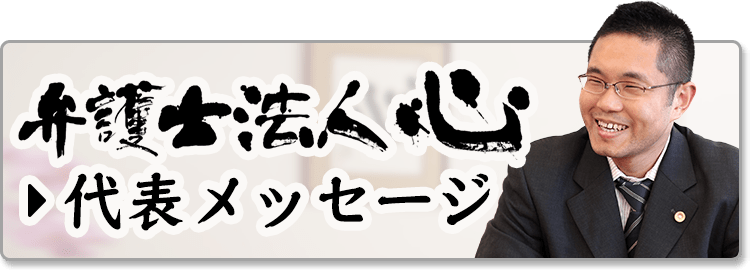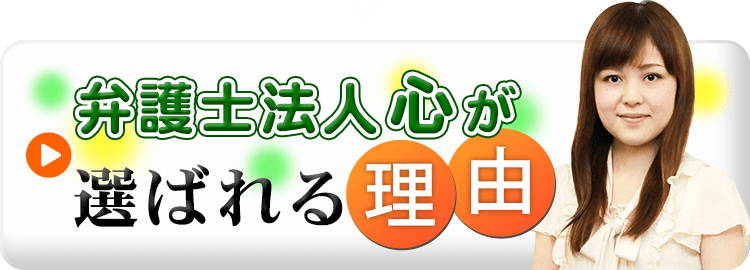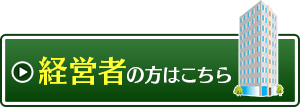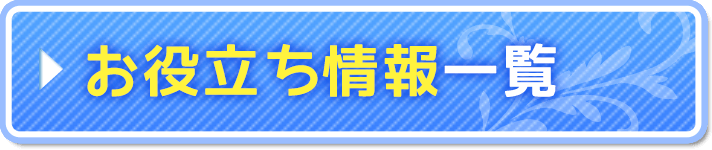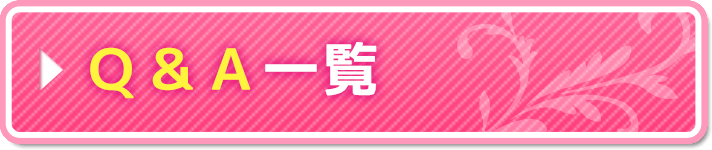「自己破産の手続」に関するお役立ち情報
自己破産で管財事件になるケース
1 同時廃止・管財事件
⑴ 同時廃止
「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認めたとき」(破産法216条1項)は、破産手続開始の決定と同時に、破産手続を廃止する決定が出されます。
このように、破産手続の開始と廃止の決定が同時に出される場合を「同時廃止」といいます。
⑵ 管財事件
破産手続の開始と廃止の決定が同時に出されるのではなく、財産調査等の手続を経てから破産手続が廃止され、手続開始の決定と廃止の決定の時期がずれる場合を「異時廃止」といいます。
異時廃止の場合、「破産管財人」という、申立てを依頼した弁護士とは別の弁護士が裁判所から選任されて手続に関与することから、一般に「管財事件」(または「破産管財事件」)と呼ばれます。
2 ある程度の資力があるケース
同時廃止の要件である「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」かの判断においては、簡単に言ってしまえば、まずその管財人費用を用意できるかどうかが1つの基準となります。
自己破産が認められれば、債権者は貸したお金が一切返ってこなくなるわけですから、自己破産を認めてよいかは本来、裁判所が選任した破産管財人の調査を入れて慎重に判断されるべきものです。
しかし、そもそも返済も困難な状況で手続費用の用意も簡単ではありませんし、調査に費用がかかっても、債権者に配当されるべき財産がないことが明らかという例外的な場合にまで費用をかけて調査をするのは無益と言えるので、この場合は同時廃止となります。
東京地裁の運用では、現金33万円以上、預貯金やその他の資産を20万円以上持っている場合には、少なくとも管財人を選任する本来通りの調査が可能ということで、管財事件となります。
3 自己破産者が個人事業主であるケース
個人事業主の方の場合、事業のための借入れが絡んでいたり、経費処理がどうなっているのか不明瞭な場合が多かったりしていて、財産や負債の状況を正確に把握することが難しいことが多いです。
そのため、通常は調査のために管財事件として処理されます。
4 免責等の調査を要するケース
個人が自己破産するときは、最終的には裁判所から免責(借金を返済する責任の免除を受けること)の決定を受けることを目的とします。
免責は破産者にとっては今後の生活の再建にとって非常に重要ですが、債権者にとっては本来返してもらえるお金が返ってこないことを意味するので、誠実な債務者でないと免責を受けることができません。
そこで、借入の額が多かったり、ギャンブルや浪費等借入の経緯に問題があったり、借り入れたお金の使途が不明確であったりする場合等には、管財人によって免責が相当かの調査をすることが必要と判断され、管財事件に振り分けられます。
5 まとめ
上記のように説明したとおり、総資産額や個人事業主か否かは形式的に決まってきますので、申立ての段階で、借り入れの経緯の調査、資産調査をしっかり進めることが重要になってきます。
東京地裁では、「即日面接」といって、申立て後すぐに申立代理人と裁判官とで面談の上協議しますので、適切かつ十分な準備が求められます。